生前整理
生前整理とは?
今後の人生をもっと楽しむための準備
豊中・箕面の縁満では、相続のトータルサポートの一環として“生前整理”を承っています。
生前整理とは、元気なうちにいつか訪れる日に備えて持ち物や財産などを整理することですが、当事務所ではこれを“今後の人生をもっと楽しむための準備”と捉えています。
「まだ先の話」「縁起が悪い」「整理するような財産はない」とお考えかもしれませんが、いざ、ご自身が亡くなられた後では、自分の意思で大切なもの・思い入れがあるものを整理することはできません。
今のうちに行動に移して、心残りのない人生を歩むようにしましょう。
生前整理のメリット
- ・後に残す家族の負担を軽減できる
- ・相続について家族と話し合う良いきっかけとなる
- ・ものが整理されて、住まいがスッキリ快適になる

縁満の生前整理の特徴
ものに“第二の人生”を
当事務所の生前整理のコンセプトは、“ものにも第二の人生を”というものです。
大切なものを処分するのではなく、海外のオークション会場に持ち込み、そこで使い道を見つけるなどして、ものが受け継がれていくようにします。
整理後のものの使用状況をご報告
例えばオークションを通じて海外へ移された場合でも、大切なものが現地でどのように活用されているのか、使用状況をご依頼者様へご報告いたします。
こんなものを引き取らせていただきます
家具
- ・ソファ
- ・ベッド
- ・本棚
- ・靴箱
電化製品
- ・テレビ
- ・扇風機
- ・掃除機
- ・電子レンジ
思い入れのあるもの
- ・長年使用し続けたタンス
- ・祖父母の代からある兄弟
- ・雛人形
- ・端午の節句の兜
生前整理をご希望の方は、お気軽に豊中・箕面の縁満へご相談ください。
※食料品、植物、ペット、医薬品などの引き受けは不可

遺言書作成
相続の専門家たちが
遺言書作成をサポート
豊中・箕面の縁満では、司法書士、行政書士、弁護士といった相続の専門家たちが、ご依頼者様にとって最適な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の作成は生前対策として有効で、後に残すご家族・ご親族を無用なトラブルから守ることに繋がります。
また相続登記の手続きもスムーズに進みます。
司法書士や行政書士が遺言書の作成をサポートし、トラブル防止の観点から弁護士がアドバイスし、さらに遺言執行者の選定の際にも弁護士へ任せることができます。
当事務所だけで遺言書の作成から執行、その後の手続きまでワンストップで対応することが可能です。

遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、特に法的に無効となるリスクが低いのが“公正証書遺言”です。 反対に無効となるリスクが高いのが“自筆証書遺言”で、どの遺言書を作成するのか、専門家のアドバイスを受けて決めるようにしましょう。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言の全文を作成する遺言書です。
他の遺言書と比べて費用がかからず手続きも簡単ですが、内容に不備があって法的に無効となるリスクが高いと言えます。
また遺言者自身で管理することになるので、紛失・偽造・隠ぺいのリスクもあり、死後、相続人が遺言書の存在に気づけない場合もあります。
そして開封に際しては必ず家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言の内容を伝えて、その内容に沿って遺言書を作成してもらう遺言書です。
公証人が作成するので、内容に不備があって法的に無効となるリスクがほぼなく、公証役場が原本を保管するので紛失・偽造・隠ぺいの心配もありません。
また開封に際して家庭裁判所の検認は不要です。
ただし、作成に際して費用がかかり、証人の立ち合いが必要になります。
秘密証書遺言
作成した内容を公証人役場へ持ち込み、公証人および証人立ち合いのもと、保管を依頼する遺言書です。
遺言内容を誰にも知られずに済み、紛失・偽造・隠ぺいの心配がなく、まわりの方に遺言書の存在を知らせておけますが、自筆証書遺言同様、内容に不備があって法的に無効となるリスクがあります。
成年後見
成年後見制度で解消可能なお悩み
- ・将来、認知症などで判断能力が低下した時、財産管理などが心配
- ・判断能力が低下した際の遺産相続が心配
- ・相続の際、家族間で紛争が起こる可能性がある
- ・親の財産を同居している家族が使い込まないか心配
- ・万が一の事態に備えて、信頼のおける人に財産管理を任せたい
- ・身寄りがないので、介護や死後の手続きを信頼できる人物に任せたい
成年後見制度の利用により、こうしたお悩みを解消することが可能です。
制度の利用をお考えでしたら、元気なうちに豊中・箕面の縁満へご相談ください。
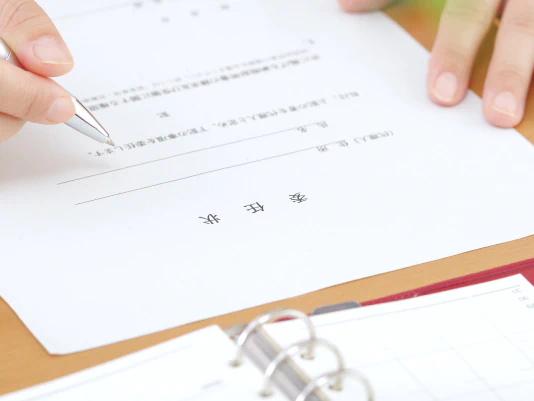
成年後見制度とは?
“法定後見”と“任意後見”に分かれます
成年後見制度とは、ご本人が認知症などにより判断能力が低下した際、本人に代わって財産管理や法的手続き、遺産相続などをサポートしてもらう制度です。
成年後見制度は大きく“法定後見”と“任意後見”に分けられます。
法定後見
認知症などでご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって成年後見人等が選任される制度です。
法定後見はご本人の判断能力に応じて、さらに次の3つに分類されます。
■成年後見人
重度の認知症などにより、判断能力がなくなった場合に選任されます。
ご本人に代わり、日常生活を除くすべての法律行為の代理権、またそれの取消権が与えられます。
■保佐人
認知症などにより判断能力が著しく低下した場合に選任されます。
ご本人が不利益を被らないための同意権、またその取消権などが与えられます。
保佐人が選任されることで、金銭の賃借や不動産の売買などを本人単独で行うことができなくなります。
■補助人
軽度の認知症などにより、判断脳能力が低下した場合に選任されます。
ご本人が望む特定の行為に対して、保佐人同様の同意権・取消権が与えられます。
任意後見
まだご本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめご自身で後見人を選任しておく制度です。
後見人と契約を締結してもすぐに効力は発生せず、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生します。
■任意後見のメリット
<自身で後見人が選べる>
元気なうちに、ご自身で後見人を選ぶことができます。
ご家族やご友人だけでなく、司法書士や弁護士などの専門家を後見人に選ぶこともできます。
<希望するサポートが受けられる>
任意後見では、いざ判断能力が低下した際、財産の管理・処分や介護など、どのようなサポートを受けたいかあらかじめ決めておくことができます。
<任意後見監督人が不正行為を監視>
任意後見では、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生します。
この任意後見監督人が契約内容通りにサポートを行っているか後見人を監視するため、不正行為が防げます。
任意後見の重要性について
ご自身がいつかお亡くなりになる日だけでなく、将来の認知症などのリスクにも備えておく必要があります。
そういう意味では成年後見制度、特に任意後見は遺言書とセットで考えることが大事です。
任意後見の場合、身寄りがない方だとその制度を知っている・知らないでその後の生活が大きく変わります。
まだまだ任意後見という制度をご存知ない方、またご存知でも上手く活用できていない方は多いので、重要な生前対策の1つとして、縁満では広く認知してもらえるように今後も積極的に啓蒙活動を行って参ります。
節税対策
最適な節対策をご提案
豊中・箕面の縁満に在籍する、税理士やファイナンシャル・プランナーなどの専門家が財産内容やご家族の状況に最適な節税対策をご提案いたします。
節税対策はできるだけ早いタイミングで始めるのが効果的ですので、将来に備えて今のうちから準備しておくようにしましょう。

節税対策の方法
相続税の節税対策として、大きく“生前贈与”と“それ以外の方法”に分けられます。
生前贈与
生前贈与とは、ご本人がまだ元気なうちにご家族などに財産を移す行為を言います。
財産を移す(贈与)の際には税金(贈与税)がかかり、課税方法には次の2つがあります。
暦年贈与課税
暦年贈与課税では、毎年(1月1日から12月31日まで)の贈与が110万円までの場合、非課税となります。
1人につき110万円なので、複数人へ計画的に贈与することで多額の生前贈与が可能で、節税効果を生み出すことができます。
ただし、贈与では基本的に双方の合意が必要になりますので、贈与する側・贈与を受ける側で贈与契約書を交わし証拠を残しておくようにしましょう。
特に小さなお子様に贈与する場合には、こうした契約書の存在が重要です。
相続時精算課税
相続時精算課税では、2,500万円までの贈与であれば非課税となり、代わりに相続発生後、受けた贈与に対して相続税が課税されます。
贈与税の節税にはなりますが、相続税の直接的な節税とはなりません。
ただし、相続税の税率は贈与税の税率と比べて低いため、通常の贈与で同額を与えるよりも税金が抑えられます。
ただし、相続時精算課税の対象となるのは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与のみとなります。
また2,500万円を超える贈与には、金額を問わず一律20%の贈与税がかかります。
それ以外の方法
生前贈与以外にも、節税対策として活用できる方法があります。
遺言書の作成
遺言書を作成しておくことで、“偶者税額軽減の特例の適用”や“小規模宅地等の評価減の特例”などの特例を利用して、節税に繋げることが可能です。
また遺言書には相続トラブルを予防する効果もあります。
生命保険の非課税枠
被相続人が生命保険に加入していて、法定相続人がその保険料を受け取る場合、【500万円】×【法定相続人の人数】が非課税枠となります。
例えば法定相続人が3人の場合、1,500万円までは相続税がかかりません。
家族信託
家族信託とは、信頼のおける家族に財産を託して、管理・運用・処分を任せるというものです。
財産の名義を家族に移すことになるので、利益が生じた場合でも贈与税の対象にはなりません。
賃貸用の不動産などの財産がある場合などによく検討されます。
二次相続
二次相続とは?
残された配偶者が亡くなった際に発生する相続
二次相続とは、先に両親のどちらかが亡くなって相続が発生した後(一次相続)、残された配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。
相続では、この二次相続のことも考慮してしっかりと対策しておく必要があります。

二次相続の問題点
法定相続人が少なくなる
残された配偶者が亡くなることで、法定相続人が少なくなるため、二次相続では一次相続よりも基礎控除額が減少します。
そのため、一次相続よりも多額の相続税が発生する可能性があります。
配偶者税額軽減の特例が利用できない
二次相続では両親がともに亡くなっているため、“配偶者税額軽減の特例”が利用できなくなります。
配偶者税額軽減の特例では、1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額まで非課税となるため、一次相続でこれを適用して相続税を抑えようとするケースが多いです。
ですが、その配偶者が亡くなると一次相続で受け継いだ相続財産を子が二次相続しなければいけなくなり、結果的にトータルの相続税が高くなる場合があります。
小規模宅地等の特例が利用できないケースも
被相続人が居住していた土地を相続する際、評価額を減額する制度が“小規模宅地等の特例”で、これにより330㎡まで評価額を80%減額することができます。
ただし、子がこの特例を利用するには両親と同居していなければならず、そうでない場合には適用されません。
そのため、親と同居していないケースで二次相続に向けて対策する場合には、速やかに同居するか、二世帯住宅にするなどの対応が必要です。
二次相続対策は専門家へご相談ください
一次相続の際、二次相続のことも考えて対応しないと、二次相続の相続税が予想していたよりも高くなる場合があります。
こうした相続の全体像を見据えた対策は、専門家でないと難しいと言えますので、ご家族だけで対応しようとせずに、相続専門事務所である縁満へご相談ください。
豊中・箕面の縁満では、税理士などの相続のスペシャリストが中心となって、二次相続も見据えたベストな相続対策をご提案いたします。






