遺産分割がまとまらない
遺産分割協議がまとまらない時は?
相続財産を相続人全員で相談して分けることになった場合、遺産分割協議を行わなければいけません。
話し合いがスムーズに進み分割できれば良いのですが、数ある相続の手続きの中でも遺産分割協議は特に紛争に発展しやすいです。
どうしても話し合いで遺産分割がまとまらない場合、次のような流れで解決をはかることになります。
調停分割
調停分割とは、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介してどのように遺産分割するのか話し合う方法です。
どうしても相続人間の主張が対立してしまう場合には、調停委員から解決案が提示されることもあります。
審判分割
調停での話し合いがまとまらなかった場合には、審判手続きに移行します。
審判分割では家庭裁判所の裁判官が相続財産の内容や相続人等の事情を考慮して、審判を下します。
審判後は、その内容に従って相続財産を分けることになります。
高等裁判所への不服申立
審判の内容に納得がいかない場合、審判後、2週間以内であれば高等裁判所へ不服を申し立てることができます。
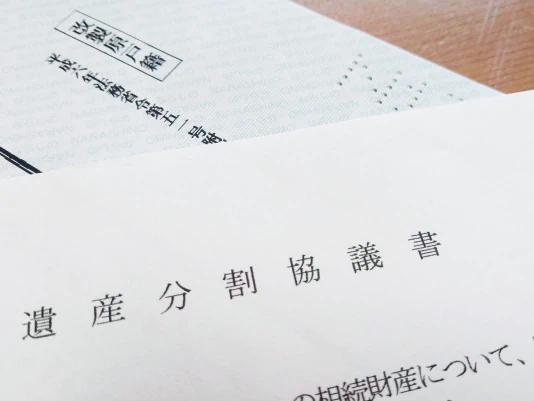
専門家からアドバイスを受けてみませんか?
遺産分割の話し合いがまとまらない際、ご家族・ご親族などの当事者だけで話し合っていても、かえって問題が深刻化してしまうケースが多いです。
こうした場合には、専門家から第三者目線の冷静なアドバイスが有効です。
豊中・箕面の縁満では、相続専門事務所として円満な遺産分割協議を目指してサポートいたします。
弁護士が紛争解決・予防
当事務所には弁護士が在籍していて、遺産分割協議の紛争をスムーズに解決させることが可能です。
またどうしても協議がまとまらず、調停・審判へ移行せざる得ない場合でも、ご依頼者様の代理人としてトータルサポートいたします。
ただ、最善なのはそうした紛争に発展する前に、弁護士などの専門家へ相談して“予防”することです。
少しでも相続をめぐって紛争が起こりそうな可能性があるなら、早いタイミングで当事務所へご相談ください。
遺留分
遺留分とは?
特定の相続人に認められた最低限の相続割合
遺留分とは、民法により特定の相続人に認められた最低限の相続割合のことです。
民法で定められているため、遺言書の内容などにより遺留分が侵害されている場合には、“遺留分侵害額請求”という手続きによりそれを取り戻すことができます。
遺留分が認められている相続人
調民法では次の相続人に遺留分を認めています。
- ・被相続人の配偶者
- ・被相続人の子(または代襲相続ができる直系卑属)
- ・被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)

遺留分侵害額請求とは?
遺留分の返還を求める行為
遺留分侵害額請求とは、民法で認められている遺留分が侵害されている際、侵害している相手に対して返還を求める行為です。
よくある遺留分の侵害のケースとして、「遺言書の遺産分割の内容が偏っている」「一部の相続人に生前贈与が行われていた」などが挙げられます。
相手と交渉して侵害された遺留分を請求
遺留分侵害額請求権を行使する際、特別決まった手順はありません。
裁判所を介する必要はなく、自身の遺留分を侵害している相手と直接交渉して請求を行います。
遺留分侵害額請求は弁護士へ
遺留分侵害額請求を行う際は、弁護士へ相談されることをおすすめします。
ご自身の遺留分が本当に侵害されているのかどうかの確認は難しく、また生前贈与による遺留分の侵害の判断の際も専門知識が求められます。
そして相手と交渉した際、素直に請求に応じてくれれば良いのですが、遺留分の侵害をめぐってトラブルとなる可能性が高いと言えます。
遺留分の侵害を適切に調査・確認し、スムーズに解決するためにも、まずは一度弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求権は1年で時効
遺留分侵害額請求権は相続発生を知ってから1年で時効となります。
時効後は遺留分侵害額請求を行うことができなくなりますので、お早めに弁護士へご相談ください。
また相続が発生したことを知らなくても、相続発生から10年経過した場合も遺留分侵害額請求権は時効となります。
相続放棄
相続放棄とは?
手続き上、“相続人でなかった”ことになります
相続放棄は相続財産を確認した際、現金や預貯金などのいわゆる“プラスの財産”よりも、借金や債務などのいわゆる“マイナスの財産”の方が明らかに多いため、そのまま相続すると不利益を被る場合によく利用されます。
相続放棄することで、その方は最初から“相続人でなかった”ことになり、マイナスの財産を受け継がずに済むようになります。
ただし、プラスの財産も同様に相続できなくなります。
このようなケースで相続放棄は検討されます
- ・被相続人が多額の借金を残していた
- ・被相続人が高額な借金の保証人になっていた
- ・相続財産が自宅だけなので、居住者にその権利を譲りたい
- ・遺産分割など、相続の手続きに煩わされたくない
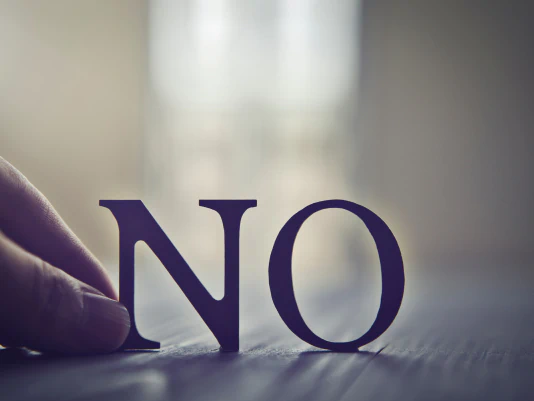
相続放棄の注意点
相続発生後3ヶ月以内に申立
相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければならず、これを過ぎると単純承認したものとみなされて、プラスの財産とともにマイナスの財産も相続しなければいけなくなります。
まわりの家族・親族との調整が必要
相続放棄するとその方は最初から相続人でなかったことになるため、次の順位の人に相続権が移行されます。
相続放棄しても借金などのマイナスの財産はなくなるわけではなく、次の順位の相続人がそれを負うことになるため、相続放棄する前にはまわりのご家族・ご親族との調整が必要です。
専門家に相談してから相続放棄を決めましょう
相続放棄の手続きは、相続放棄する本人単独で行うことができますが、その前に一度専門家へ相談するのがおすすめです。 豊中・箕面の縁満では財産内容やご家族構成などをよくおうかがいしたうえで、本当に相続放棄が適切かどうかアドバイスいたします。
本当にマイナスの財産が上回っているのか?
一度相続放棄すると、それを取り消すことは原則できません。
そのため、「マイナスの財産の方が多い」と思っていても、後から高額なプラスの財産が出てきた場合、それを相続することができなくなります。
相続放棄の手続きを行う前に、専門家へ相談して相続財産を詳細に調査・確認してもらい、相続放棄するべきかどうかアドバイスを受けるようにしましょう。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなります
手続きを行う前に不動産を売却するなど相続財産を処分したり、名義変更したりしてしまうと、相続放棄できなくなります。
そうしたことがないように、相続放棄を検討した時点で一度専門家に相談するようにしましょう。
その他揉め事
寄与分をめぐるトラブル
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人へ、他の相続人よりも多く相続財産を渡すことを認める制度です。
何をもってして“特別な貢献”とするかは判断が非常に難しく、寄与分を主張する相続人とそれを否定する相続人間で争いとなるケースが多いです。
長年、親の介護をされてきた方などで、寄与分を主張したいという場合には、介護記録を残しておくだけでなく、介護の実績を反映させた遺言書を作成しておいてもらうなどの対策が必要です。

遺言書の内容をめぐるトラブル
親と同居していた相続人が、自身にとって都合の良いように遺言書を作成させるケースがあります。
この場合、同居していた相続人が「自分は長年、介護し続けていたのだから、これぐらい受け取って当然」と考えていることが多いです。
こうした場合には、まずは遺言書の遺産分割の内容が他の相続人の遺留分を侵害していないかを確認し、侵害されていれば遺留分侵害額請求により返還を求めることが可能です。
また、家庭裁判所に遺言無効の調停を申し立てるという方法もあります。
特別受益をめぐるトラブル
生前贈与などで特定の相続人が利益を得ていた場合、それを“特別受益”とし、受け取った利益分を遺産分割の計算に入れて修正することが可能です。
これを“特別受益の持ち戻し”と言います。
特別受益とみなされるものとして、結婚の際の持参金・支度金、高等教育のための学費、マイホームの購入資金の援助などが挙げられます。





