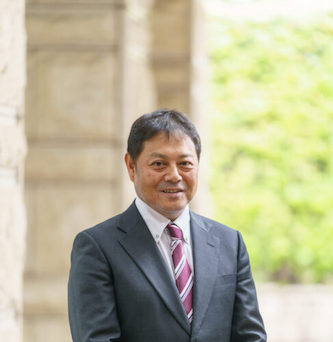遺産分割協議の前に、葬儀費用を支払うために、親の預金口座から引き出すことが可能か解説します

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、弁護士の藤原です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
今回は「遺産分割協議の前に、葬儀費用を支払うために、親の預金口座から引き出すことが可能か」について詳しく解説します。
1 従来の取り扱い
被相続人の死亡後、その方の財産は相続人全員の凖共有財産となります
したがって、遺産分割協議が終わっていない状態で、相続人の一人が勝手に口座から引き出すことは、他の相続人の権利を侵害し、許されないのが原則です。
金融機関も預金口座の名義人が死亡したことを確認すると、相続人が勝手に引き出すことを防止するために、その口座を凍結し、他の相続人全員の同意がなければ、預金の引き出しが事実上もできませんでした。
2 民法の改正
(1)民法909条の2
実際には、親の葬儀費用について、親の預金口座を利用する場合もあり、他の相続人全員の同意を短期間で得ることが困難な場合もあります。
そこで、令和元年7月1日施行の民法改正によって、遺産分割前でも、預貯金の一部を相続人が単独で引き出せる制度が新設されました。
これが民法909条の2になります。
民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」と規定されています。
(2)引き出しが可能な金額に上限がある
相続開始時の預貯金債権の額(各口座ごと)の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額が、単独で払戻しを受けることができる額となります。ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、150万円が限度となります(平成30年法務省令第29号)。
(3)具体例
具体例を挙げると、亡くなった親の銀行口座に600万円の預金、相続人として、子供2人の場合、引き出せる額は100万円(600万円 × 1/3 × 1/2)になります。
3 注意点
(1)引き出した金額も遺産分割の対象となる
単独で引き出しても、その金額は遺産分割時に相続分として清算されます。つまり、遺産を先に一部受け取ったとみなされるため、他の相続人の取り分が減るわけではありません。
特に葬儀費用として使用した場合でも、葬儀費用は喪主の負担であるとされることから、預金から引き出し、葬儀費用として使用しても、他の相続人が同意しない限り、相続財産から、葬儀費用を除き、残りを他の相続人と法定相続分で分けることができないので、注意が必要です。
(2)相続放棄が認められない可能性がある
預金口座の引き出しにより、相続を単純相続したものとして、相続放棄が認められない可能性があります。相続放棄を検討されている場合は、引き出しを行わない方が良いです。
まとめ
ご不明点などある方は、相続の相談を専門に対応している私たち縁満に、いつでもご相談ください。
あなたの相続手続きを全力でサポートいたします。