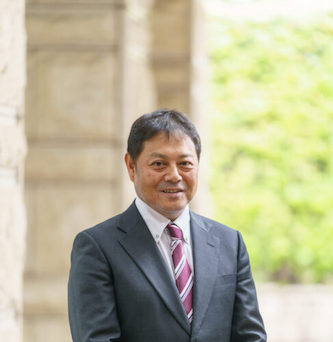遺産分割協議書とは?作成の流れと注意点を行政書士が解説
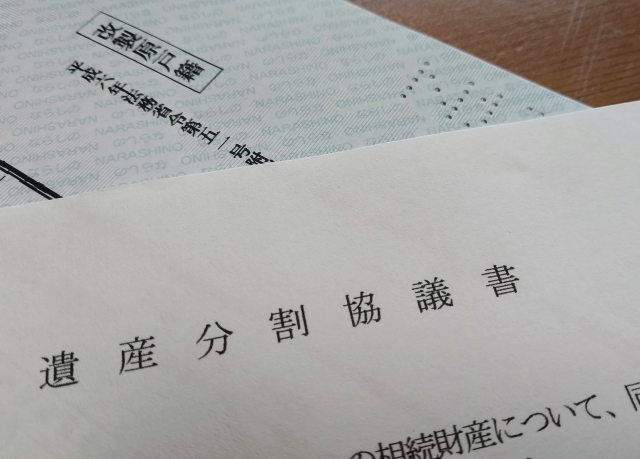
豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、行政書士の前川です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
今回は、「遺産分割協議書を作成する流れと注意点」について解説したいと思います。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人でどのように分けるかが問題となります。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、合意に至った内容を文書にする必要があります。
これが「遺産分割協議書」です。
この記事では、遺産分割協議書の役割と作成の流れ、注意すべきポイントについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
- 1. 【遺産分割協議書の役割】相続人全員の合意内容を文書化し、不動産や預貯金の名義変更・相続税申告などの法的手続きに必須となる重要書類。
- 2. 【作成の流れ 】①相続人の確定 → ②財産の把握 → ③分割協議 → ④協議書作成(署名・実印) → ⑤必要書類とともに提出。
- 3. 【注意点と専門家活用】相続人全員の署名・押印が必須、不備やトラブルを避けるため行政書士など専門家に依頼するのが安心。
遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意に基づいて、誰がどの財産を相続するのかを記載した書面です。
この書面は、相続税の申告や不動産・預貯金の名義変更といった手続きにおいて、法的な根拠となる重要な書類です。
たとえ相続人間で口頭合意ができていても、金融機関や法務局などの手続きでは書面の提出が求められます。
(ただし、遺言がある場合をのぞく)
協議書作成が必要な理由

預貯金や不動産、株式などの財産をどのように分けたかが書面で明らかでなければ、これらを被相続人名義のまま預り管理している金融機関や法務局は、実際に相続した者に安全に払戻や変更などの手続きが行えないのです。
また、相続税の申告が必要である場合にも、税負担者を判断するために協議書が必要です。
作成の流れとポイント

1. 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人全員を明らかにします。なお、相続権がある者が一人でも欠けた協議は無効です。
2. 相続財産の把握:不動産・預貯金・株式・負債など、全財産を調査・評価します。
3. 分割協議:相続人全員で話し合い、どの財産を誰が取得するかを決定します。
4. 協議書の作成:合意内容を文書化し、相続人全員の署名・実印押印を行います。
5. 必要書類とともに提出:不動産登記や金融機関手続きに用います。
注意すべきポイント

・相続人全員の署名・実印が確実になされる必要があります。
・一部の相続人が行方不明・連絡不能な場合は、家庭裁判所での手続きが必要になることも
・作成後は紛失しないよう複数部作成し、少なくともコピー等を保管しておくことを推奨します
専門家に依頼するメリット

協議内容が複雑であったり、相続人間で意見の食い違いがある場合には、第三者である行政書士などの専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、協議書の形式的な不備を避け、法的に有効な書類を確実に作成できます。
相続は、人生の中で何度も経験するものではありません。
だからこそ、専門家の力を借りて安心かつ確実に手続きを進めることが大切です。
当事務所では、初回相談無料で遺産分割協議書の作成をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。