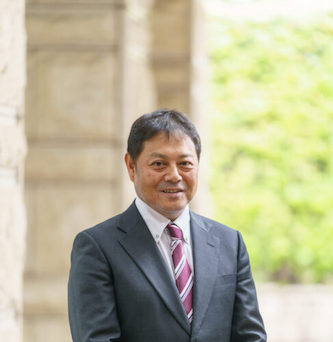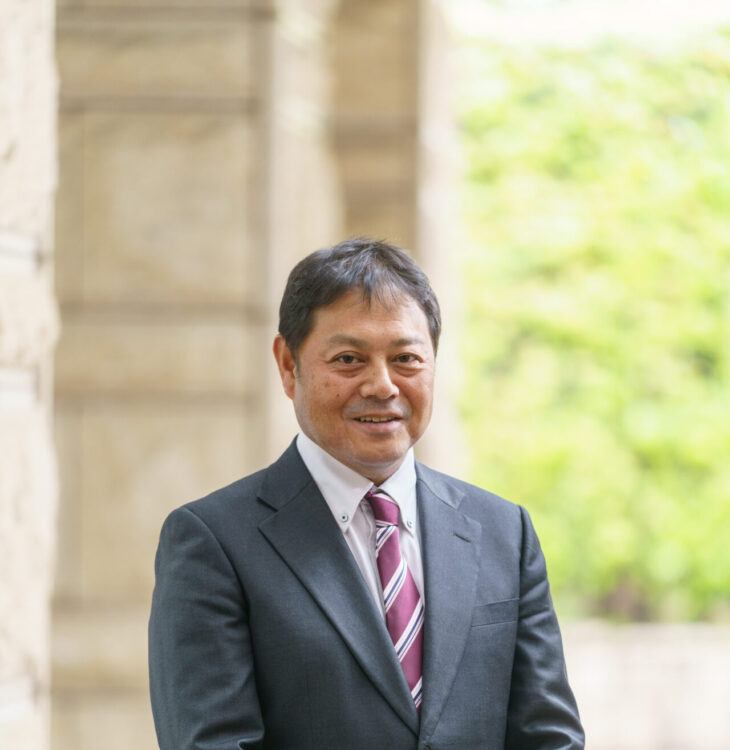相続した不動産を売却する「手続き」「必要書類」「税金」について解説します

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、司法書士の清原です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
相続した不動産を売却する際は、故人の大切な資産を適切に扱い、税金や手続きの複雑さを乗り越える必要があります。
このブログでは、相続した不動産の売却における手続き、税金、特別控除、そして注意点について、専門家の知見を交えながら詳しく解説します。
- 1. 相続登記(名義変更)が必須
- 2. 売却には税金・費用がかかる
- 3. 専門家に相談することでスムーズに進む
1.相続した不動産を売却する主なケース

相続した不動産を売却する主な理由は以下の通りです。
• 相続したが利用しない場合
例えば、親の自宅を相続した子がすでに自身のマイホームを所有しており、実家に戻る予定がない場合などです。不動産を保有しているだけでも固定資産税が発生するため、遊休地や空き家として放置するより売却して有効活用する方が良いとされます。
• 相続税の納税資金を確保するため
相続税は原則として現金での納付が求められます。相続財産が不動産ばかりで納税資金が不足する場合、不動産を売却して納税資金に充てる必要があります。
• 換価分割(かんかぶんかつ)を行うため
相続財産を現物で公平に分割することが難しい場合、不動産を売却して現金に換え、その売却代金を相続人全員で分け合う方法です。
2.相続不動産売却の必須ステップ:相続登記(名義変更)

相続した不動産を売却するためには、まず相続登記(名義変更)手続きを行う必要があります。
(令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。)
~不動産の相続登記の義務化について~
不動産を相続等で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。
この期限を過ぎて相続登記をせずに放置した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
施行前に発生した相続も同様に義務化の対象です。
~相続登記の手続きの流れと必要書類~
相続登記の申請手続きは以下の流れで進めます。
①必要書類の収集
以下の書類を役所等で収集します。
-
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
- 相続する不動産の全部事項証明書(法務局で取得)
②相続登記申請書を作成します。
③法務局への申請
相続不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
④登記識別情報通知書(昔の権利書)が法務局から発行されます。
以上の流れで手続きを行いますが、ケースによって必要書類が異なるため、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼すれば、登記申請書の作成だけでなく、印鑑証明書以外の必要書類の取得も代理で行ってもらえるため、手続きが非常に楽になります
2.相続不動産の分割方法
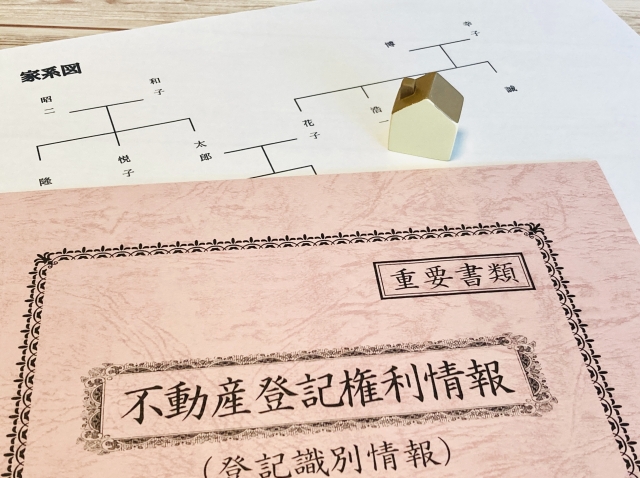
不動産は現金のように簡単に公平に分割できないため、分割方法について理解しておくことが重要です。
主な分割方法は以下の4種類です。
• 現物分割
現金や車、不動産などの財産を現物のまま各相続人に分ける方法です。単独所有にできるメリットがありますが、法定相続割合で公平に分けることが難しい場合があります。
• 換価分割
不動産などの遺産を売却して現金化し、その現金を相続人で分割する方法です。
法定相続分で公平に分けられるメリットがある一方、売却の手間がかかります。
売却を前提とする場合:代表者一人の名義に相続登記し、売却してから他の相続人と売却代金を分ける「単独登記型」が便利です。
この場合、遺産分割協議書に換価分割目的で遺産を取得することを明記することで、代表者が受け取った現金を他の相続人に配分する行為が贈与とみなされることを防げます。
• 代償分割
特定の相続人が財産を多く相続し、その代償として他の相続人にお金(代償金)を支払うことで不公平感を調整する方法です。特定の相続人に不動産を引き継がせられるメリットがある反面、代償金を支払う側の経済的負担が大きくなります。
• 共有分割
遺産を主に法定相続割合で共有する分割方法です。法定相続分で公平に分けられるメリットがありますが、将来的に所有者が増えすぎて売却手続きが複雑化するリスクがあります。共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意(売却自体と価格)が必要となります。
相続した不動産を売却する場合には、「現物分割」「換価分割」が一般的です。
3.相続不動産売却時にかかる税金と費用

相続した不動産を売却すると、いくつかの税金と費用が発生します。
これらの知識を備えておくことで、税負担を低く抑えることが可能です。
①譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
・概要:不動産(土地や建物)を売却して利益(譲渡所得)が得られた場合に課される税金です。
・計算方法: 譲渡所得 = 譲渡収入金額 − 取得費 − 譲渡費用
・譲渡収入金額:売却価格に、買主から受け取った未経過の固定資産税精算金額も含めます。
・取得費:故人が生前に購入したときの金額で計算します。購入時の仲介手数料、測量費、造成費用、改良費なども加えられます。建物の取得費は、購入・建築代金から保有期間に応じた減価償却費を差し引きます。
・取得費が不明な場合:原則として売却価格の5%を取得費とすることができます。
ただし、この場合、課税される税金が高額になる可能性が高いため、預金通帳の出金記録や当時のパンフレットなど、取得費を証明する代替資料を探すことを強くおすすめします。
・譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙代、建物の取り壊し費用などが該当します。
・税率:土地や建物の所有期間によって異なります。この所有期間は、被相続人が不動産を所有を開始した日から売却した年の1月1日までで数えます。
【短期譲渡所得(所有期間5年以下)】
所得税 30.63%(復興特別所得税0.63%含む)+ 住民税 9% = 計39.63%
【長期譲渡所得(所有期間5年超)】
所得税 15.315%(復興特別所得税0.315%含む)+ 住民税 5% = 計20.315%
所有期間が5年前後の場合は、売却時期をずらすことで税率を下げられる可能性があります。
②登録免許税
・概要:相続登記(所有権を故人から相続人へ変更する手続き)にかかる税金です。
・計算方法:固定資産税評価額 × 税率0.4%(相続人が取得した場合)。
③印紙税
・概要:相続不動産の売却時に作成する「売買契約書」などにかかる税金です。
・税額:契約金額に応じて定められており、令和9年(2027年)3月31日までに作成された契約書は軽減措置の対象となります。
④その他の費用
・仲介手数料:不動産売却を業者に依頼した際に発生し、売却価格に応じて上限が定められています。
・土地の確定測量費:土地の区画について測量を実施した場合に発生します。
・建物解体費用:土地に建物が建っている場合、取り壊すときにかかる費用です。
■注意点■
税金や費用は相続人全員で負担 相続不動産の売却にかかる税金や費用は、その相続財産を取得した相続人全員で負担することになります。
代表者が売却手続きを進めたとしても、税金や費用は取得した相続人全員で分担する必要がある点に注意しましょう。
4.譲渡所得税を節税できる特例

相続した不動産を売却して利益が出た場合でも、特定の特例を適用することで譲渡所得税を節税できる可能性があります。
これらの特例には「○○から3年以内に売却すること」といった適用要件が設けられていることが多く、相続不動産を売却するなら、3年以内が節税効果が高い目安となります。
①相続税の取得費加算の特例
概要:相続税を納税した場合、その相続不動産に対して「相続税」と「譲渡所得税」が二重に課税されるのを防ぐため、支払った相続税額のうち一定金額を譲渡所得税計算時の「取得費」に加算できる特例です。
これにより、課税譲渡所得金額が減少し、譲渡所得税を軽減できます。
■主な適用要件
・相続または遺贈により財産を取得した者であること。
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
・その財産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること(つまり、相続開始から3年10ヶ月以内の売却が目安となります)。
・被相続人の所有期間は問われません。
②空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
概要:相続した家屋が空き家となり売却する場合、その売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる特例です(令和9年12月31日まで)。
譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得税をゼロにできる可能性があります。
注:令和6年1月1日以後の譲渡で、空き家を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は最高2,000万円となります。
■主な適用要件
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
区分所有建物登記がされている建物(マンションなど)でないこと。
相続開始の直前において被相続人が1人で居住していた家屋であること。
売主が相続や遺贈でその不動産を取得したこと。
相続開始日から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
売却代金が1億円以下であること。
相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に利用していないこと。
一定の耐震基準に適合していること(または家屋を取り壊してから売却すること)。
親子や夫婦など特別な関係がある人への譲渡ではないこと。
5.相続した不動産が売却できない場合の対処法と注意点

相続した不動産がすぐに売却できない場合も考慮が必要です。放置すると様々なリスクが生じます。
• 「特定空き家」指定のリスク
そのまま放置され、衛生上有害、建物倒壊の危険、地域の景観を損なうなどと判断されると「特定空き家」に指定される可能性があります。指定されると固定資産税の特例措置から除外され、固定資産税額が最大6倍になるほか、最大50万円の過料が科せられる場合があります。
• 「管理不十分な空き家」への課税強化
特定空き家に指定されていなくても「管理不十分」と判断された空き家は、固定資産税優遇の対象から外され、課税が強化される方針が固まっています(令和5年12月13日より実施)。
売却できない場合の選択肢
1. 相続土地国庫帰属制度の活用
相続した土地の所有者が、法務大臣の承認を受けることでその土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。
令和5年(2023年)4月27日から利用可能となっています。
2. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
一定の要件に当てはまる土地の譲渡価格が上限800万円に引き上げられ、100万円の特別控除が延長されました。
令和5年1月1日〜令和7年12月31日の譲渡が対象です(コインパーキングは対象外)。
3. 不動産会社による直接買取(買取)
買い手が見つからない場合、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法です。
迅速な現金化が期待できますが、仲介売却よりも売却価格は市場価格の7〜8割程度に下がる傾向があります。
4. 更地での売却
相続した家屋がかなり古い、空き家の期間が長く管理不十分、住宅需要が少ない土地にあるといった場合、建物を解体して更地で売却することを検討できます。
解体費用がかかることと、住宅用地の特例が解除され固定資産税が増加することに注意が必要です。
悪徳事業者への注意
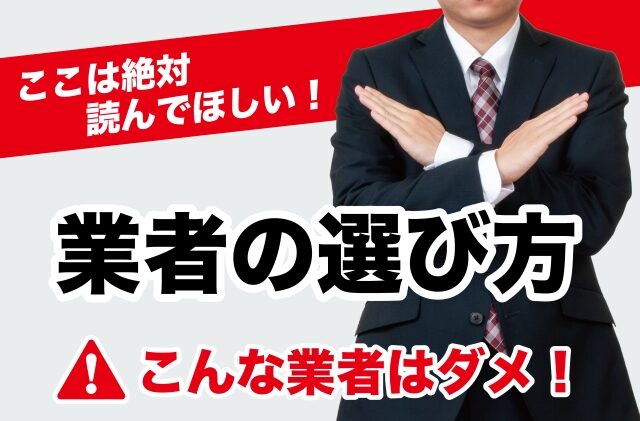
売却しにくい「負動産」の処分を請け負うと持ち掛けてくる悪徳事業者が増えています。
焦って違法なサービスに飛びつく前に、過去に行政処分を受けていない国土交通大臣や都道府県知事の認定を受けた登録不動産業者、または相続不動産に詳しい税理士に相談することが重要です。
相続不動産売却におけるその他の注意点と専門家の活用
■契約不適合責任
売主として、売却後に判明する隠れた欠陥(雨漏り、給水管の不具合、土壌汚染など)について責任を負う「契約不適合責任」に注意が必要です。後々のトラブルを避けるため、分かる範囲の情報はすべて不動産会社に伝え、心配な点は事前に報告しましょう。
■売却期限は3年以内が目安
上述の「相続税の取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」など、相続不動産で利用できる特例の多くが「相続開始後3年以内」を要件としています。
不動産の売却には名義変更から引渡しまで半年以上の時間がかかるため、これらの特例活用を目指すなら、3年以内を目安に売却活動を始めることがポイントです。
■取得費が不明な場合の対応
取得費が不明の場合、売却価格の5%を概算取得費とすることは可能ですが、これにより課税される税金が高額になる可能性が高いです。
安易に5%ルールを適用せず、以下の代替資料を探すことを強く推奨します。
・新築物件の場合、当時の販売ディベロッパーから購入当時の売買契約書の写しをもらう。
・当時仲介してくれた不動産会社や売主から購入当時の売買契約書の写しをもらう。
・通帳の出金履歴から購入額を推測する。
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書から購入額を推測する。
・抵当権設定額から購入額を推測する。
・市街地価格指数や着工建築物構造別単価などの公表資料から取得費を算定する。 これらの資料が揃った場合、後から否認されないように税務署に相談することも重要です。
■信頼できる不動産会社の選定
相続した不動産のスムーズな売却には、高く売ってくれる売却に慣れた不動産会社を探すことが最も重要です。
不動産会社にはそれぞれ得意分野や地域特性があり、同じ物件でも査定額が大きく異なることがあります。
■相続税の特性と専門家の重要性
相続税は、申告までの期限が短く(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)、税務調査率が高く(5件に1件)、そして納め過ぎが多い(8割)という特性があります。
特に不動産・土地の評価は複雑であり、税理士の評価方法によって支払う相続税額が大きく変わる可能性があります。
相続税専門の税理士は、不動産の適切な評価を行い、最大限の節税を実現する知見と経験を持っています。
また、相続税還付の実績を持つ税理士法人もあります。
相続した不動産の売却は、税金だけでなく、様々な手続きが絡む複雑なプロセスです。
相続税専門の税理士や司法書士、不動産の専門家に相談することで、手続きの煩雑さを軽減し、適切な節税対策を講じることが可能です。多くの専門家は初回無料相談を提供しています。
まとめ

相続した不動産の売却は、相続登記から始まり、売却活動、税金計算、確定申告に至るまで、多岐にわたる手続きと専門知識を要します。
まず、相続登記(名義変更)が必須であり、令和6年4月1日からは3年以内の申請が義務化されました。
不動産の分割方法としては、換価分割が売却を前提とする場合に有効な手段です。
売却時には、譲渡所得税、登録免許税、印紙税などの税金が発生し、これらの税金と費用は相続人全員で負担します。
譲渡所得税の節税には、「相続税の取得費加算の特例」(相続開始後3年10ヶ月以内)や「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」(相続開始後3年目の年末まで)といった特例の活用が重要です。
これらの特例の適用には期限があるため、3年以内を目安に売却を進めるのが賢明です。
取得費が不明な場合でも、安易に売却価格の5%とせず、可能な限り当時の書類や代替資料を探す努力をすることが、税負担を抑える上で非常に重要です。
売却が難しい場合には、直接買取や更地化、あるいは相続土地国庫帰属制度などの選択肢も検討できます。
手続きの複雑さや税制上のメリット・デメリットを考慮すると、相続に詳しい税理士や不動産の専門家に相談することが、スムーズかつ最適な結果を得るための最善策となるでしょう。
両親から受け継いだ大切な不動産を、気持ちの面でも金銭の面でも納得のいく形で売却できるよう、
ぜひ専門家の力を借りながら計画的に進めてください。
もし相続不動産の売却に不安がある場合は、相続に相談窓口~縁満~へご相談ください。相続手続きを支援する弁護士・行政書士・司法書士・税理士が所属しております。
土日祝日・夜間も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。